
勉強でも、スポーツでも、練習でも、仕事でも、『本質を求めること』は非常に重要なポイントとなります。
計算問題でミスを連発したとき「ケアレスミスだからしょうがない」と考える人は、いつまで経っても同じミスを繰り返し続けます。
“大会で優勝する”という目標を掲げたとき「優勝するためには何をどれくらいの実力にまで身につけなければいけないのか?」「そのためにはどんな練習をどの順番で、どのくらいの期間行うべきか?」を考えてから練習しなければ、目標が無いのと何も変わりません。
「何が出来ていないのか?」
「まず何からやるべきなのか?」
この考え方を身につけるコツが【なぜなぜ分析】にあります。
「なぜなぜ分析」とは?
さて、最初の問題を見てどう思いましたか?
おそらくほとんどの人は、『1』か『2』を選択しながらも
でもどうせこれって『3』なんだろうな……
でもこれどういう意味? 関係あるん?
と思ったのではないでしょうか?
ぶっちゃけ『3』の内容はこれに限るわけでなく、場合によって全然異なる内容になります。
要は、ケガしたことに対して「ケガするな」と叱ったり注意を促しても意味がないという話です。
何か原因があったから転倒しケガをしたのです。ならば、その原因を追及する方が重要です。
であるにも関わらず、ケガしたことに言及をしても、原因は放置状態にしかならないのです。
今回の問題を例に挙げると、
- なぜ従業員が転倒したのか?
→ 現場を調査すると、従業員が作業していた足場が水浸しになっていた。 - なぜ足場が水浸しになっていたのか?
→ すぐ近くにある機械から水漏れが発生していた。 - なぜ機械から水漏れしていたのか?
→ 中の部品の一部が劣化しており、損傷によって水が漏れ出ていた。 - なぜ部品が劣化しているのに気付けなかったのか?
→ 頻繁に機械の点検を行う習慣がなかった - なぜ点検を行う習慣がなかったのか?
→ 業務内容に点検する項目がない
または、点検するほどの時間的余裕がある業務内容になっていない
結論:業務内容の見直し(頻繁な機械の点検・整備&作業現場の清掃)
といった具合に疑問と原因を繰り返す流れで、根本的な原因をしっかり突き止めることができます。
この事例でいえば、もしも「ケガするな!」と叱るだけで終わっていたら、部品の劣化・損傷に気付くことが出来ませんでした。場合によってはより甚大な事故や損害が起きたかもしれません。
こうしてみると、最初の問題の選択肢『1』と『2』は、何の対策にも解決にもなっていないことがよく分かります。
こうやって「なぜ?」「どうして?」という疑問を繰り返して問題点を掘り下げ、真相を究明していく手法が【トヨタ式『なぜなぜ分析』】と呼ばれています。
“原因”は見つかるまで探し続けるもの
これはトヨタでの業務改善で活用される手法なのですが、『パッと見て分かる【原因】ではなく、より根本的な【真因】を見つけ出せ』という考え方です。(以下書籍より一部引用)
 |
根本的な原因は、すぐ分かるような要素にはありません。
「どうせ◯◯が原因でしょ」とすぐに浮かぶものは表面的でしかなく、「どうしてそうなったのか?」と順を追って辿るように思考を巡らせなければ、本当に解決するべき真因に行き着くことは非常に困難です。
昨今でも中国・ギリシャ・インドなどで凄惨な列車事故が発生していますが、かつて日本でも多くの命を奪った哀しい事故がありました。
車両・運航・航空など乗り物を事業にする企業は、人への安心・安全が最優先であることが絶対条件であるはずです。
そのバランスが崩れた瞬間、悲劇が訪れるのは当然といえば当然です。
『時間を守ること』『ルールを守ること』は安全を保つうえで大切ですが、時には地獄が手招きする状況へひっくり返ることを覚えておかなければいけません。
これは、真因を正しく導き適切に改善しなければ、類似する事故が再び発生しうる可能性のある事例です。
『本質を求めることが大切』というより『本質を求めなければ危険』ということです。
「あれ、どこにやったっけ……?」と、探し物がいくら探しても見つからないことが日常で起こり得ます。
探し物が見つからないのは、『見つかるまで探し続けることをしないから』。
見切りをつけて良いものなのか、探し続けなければならないものなのか、見極める選球眼を養う必要があり、養う為には常に真因を見つけ出すクセをつける必要があります。
まずは勉強に応用してみよう
真因を見つけ出すクセをつけるために、「なぜ?」「どうして?」と疑問を抱き、自力で解決する習慣を持つようにします。
そもそもこの習慣は、幼い頃には誰にだって持ち合わせていた素養です。
「空はどうして青いの?」
「赤ちゃんはどこから来るの?」
「飛行機はどうやって飛んでるの?」
こういった純粋な疑問を「そういうものだから」などと大人達からはぐらかされたりしているうちに、次第に持たなくなってしまいます。(あるいは誰かが答えてくれるのに甘えて、疑問に対し「わかんない」で終わらせてしまいます。)
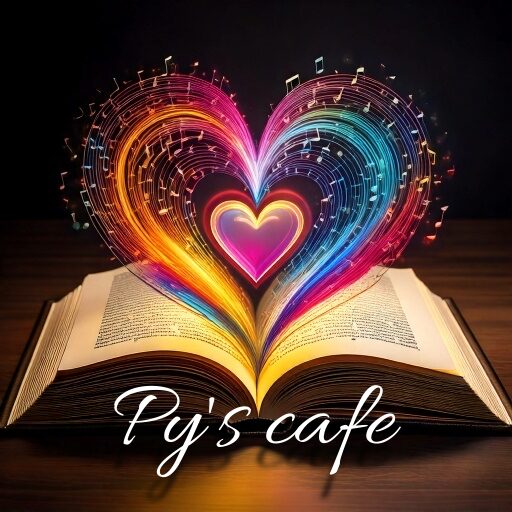 Py’s cafe
Py’s cafe 



