打楽器奏者として上手くなるためには、音の鳴らし方や体の使い方に対して精密に理解し、細部まで精密に思い通りコントロールする知識と技術が必要となります。
打楽器は音ゲーではない
初めて打楽器を触った時から、普通ならば腕の動かし方や指の使い方などを細かく気にしながら叩く研究をすることはないと思います。
なにせ、何も考えずに適当に叩いても音が鳴るのが打楽器です。
自分の身体の使い方よりも、目の前の楽譜通りにリズムやテンポを守れるように練習する日々を送る方が当たり前であり、ほとんどの中学生・高校生の打楽器奏者がそのはずです。
しかし、これでは打楽器は上手くはなれません。

ただ音符のタイミングを取れるように練習するだけでは、『太鼓の達人』だとか、『プロセカ』や『バンドリ』などの音ゲーと大してやることは変わりません。
けれどそれだけでは、新たな楽譜を向き合う度にイチから練習をしなければならず、そしてそれを繰り返していると打楽器奏者としての実力はいつまで経っても向上しません。
なぜなのか?
それを解き明かしていきましょう。
スティックの動き方
てこの原理
まず、叩く時のスティックの動作について説明します。
これは打楽器奏者として必ず知らなければならない初歩ではありますが、打楽器指導者が居ないために伝えられないまま打楽器を奏する学生が多くいます。
詳しく知らないという人は、絶対に覚えておいてください。

『てこの原理』という物理法則は覚えていますか?
小学生の時に理科で習いました。これが打楽器を演奏するときに登場しています。
打楽器を演奏するにおいて、こういった物理法則が非常に重要です。
打楽器を叩く時は、この物理法則に従った運動がスティックで行われることとなります。
スティックは、基本として親指と人差し指で挟むように持ちます。

この親指と人差し指で挟んだ位置が、スティック動作の『軸』となり、『支点』となります。

スティックを持つ時に意識しなければいけないのが、「軸(支点)はズレてはいけない」ことです。
軸(支点)がズレると、作用点のエネルギーがそれに比例して変動します。
腕の動きやスティックの動きが、ロボットのように全く同じ動作を再現した場合、
・軸がスティックの先(チップ側)に寄ってしまえば、作用点に伝わるエネルギーが減るため、その分音量が減少します。
・反対に、軸がスティックの根本(腕側)に寄ってしまうと、作用点に伝わるエネルギーが増えるため、その分音量が増加します。

現実的にはこの軸だけの影響で音量の変化がなされるということは有り得ない話ですが、大切なのは「スティックの持ち方1つ気にすることが出来ないだけで、重大な悪影響を及ぼす危険性がある」ということです。
初歩のことであるがゆえ、早い段階で注意しておかないと悪いクセが定着してしまい、後々で修正するのがとても大変なこととなってしまいます。
ぜひとも注意を怠らないようにしましょう。
腕の使い方
叩く時は、よほど高速連打をしない限り腕を使います。
上記でスティックの軸1つで悪影響が出る、と述べましたが、この『腕の使い方』の方がもっと大きな影響を及ぼします。

そもそも人体構造上の話ですが、腕は『肩・肘・手首・指』という4種の関節を曲げることによって広い腕の可動域を可能としています。
スティックを使って打楽器を叩く際、この中の『肩・肘・指』を主軸に、リズムの速さや音量の大きさによって使い分けています。
(『手首』ももちろん使いますが、意識して使い過ぎると腱鞘炎になる危険性が高くなるので、基本的に叩き方のレクチャーの時に『手首』を軸にはお勧めしません。手首は常時、力まずゆる〜くしてるだけでOK)
肩が主軸の叩き方

テンポが遅い時、音符同士の間隔が広い時、音量が欲しい時は、肩を大きく使って叩きます。
ティンパニやバスドラム、クラッシュシンバル等、楽器が大きいもしくは音量を大きく鳴らす必要のある楽器は、この肩を主軸とした叩き方が一般的です。
腕は背中の肩甲骨から動きます。叩く動作をゆっくり行う時、肩甲骨が動いている感覚をよく確かめながら叩いてみましょう。
肘や指は全く使わない、というわけではありません。あくまで『肩・肘・指』の中で『肩』を一番大きく動かすというだけであり、肘や指も、肩の動きに合わせてしなやかに動かします。
肘が主軸の叩き方

テンポが速くなると、肩を大きく動かしていてはタイミングが間に合わなくなるか、非常に忙しない動きとなってしまいます。
速く叩かなけばならないのに大きく振りかぶっていると、スティックに伝わるエネルギーが遠心力によって余分に増幅してしまい、ムチで叩くような痛くうるさい音を鳴らしてしまいます。
そのため、この場合は肘を主軸にして叩きます。
マーチングパーカッションでは、ショルダーを背負うため肩が不自由になる上、腕と楽器との距離が強制的に一定に保たれます。テナードラムのような楽器を叩くこともあるので、見た目の統一性をもたらす意味も含めて、マーチングパーカッションの演奏の際はこの肘を主軸にした叩き方が基本となります。
テンポは約80〜160くらいであれば、よほど細かい音でない限り、この肘を主軸にした叩き方を行うことが多いでしょう。
なので、最も基本となる叩き方がこれになります。基礎練習で一番使うので、よく練習しましょう。
もちろん、肩や指を全く使わないわけではありません。肘の動作に合わせて、固まらないよう、付随した動きが出来るようにしましょう。
指が主軸の叩き方

テンポ約160以上の16分音符を叩く時、ティンパニのロールをするとき等は、この指が主軸の叩き方をします。
非常に速い連打を求められる場合、腕を動かしていては到底間に合いませんし、かなりチカラが入ってしまい身体にも悪影響を及ぼしかねません。
そのため、速ければ速いほど、肩や肘をほとんど使わず、指先だけでスティックをコントロールすることとなります。
ただ、この指先だけの叩き方はとてつもなく難しい技術となっています。容易に手を出してはいけない領域なので、他の技術を確実にマスターし、身体の使い方を完全に思い通りに操れるようになってから挑戦することをお勧めします。
イチから打楽器の基礎を習得するならば、この技術はスタートから2年くらいは関わらないくらいのつもりでいましょう。
複合して腕を使い叩く

以上の3つを分けて説明しましたが、これらは基準として『テンポの速さ』によって使い分けるのが最も分かりやすいです。
音大入試ではよく『テンポ30ほどから開始し、ゆっくり一定に加速し、自身の最高速度の連打まで到達したら3秒ほどキープし、加速した時と同じくらいの時間をかけて一定に減速し、開始したテンポまで戻る』という実技試験が行われます。
これも、上記3つの段階をそれぞれ習得し、その上『肩基準から肘基準への移行』『肘基準から指基準への移行』といった叩き方の変化をムラなくスムーズに行えるか審査するためのものです。
これだけで、その人の打楽器の実力がかなり分かってしまうほど非常に重要な初歩テクニックとなっています。
どんなテンポでも楽に思い通りに叩けるようになるには尋常ならざる練習量と集中力が必要となりますが、上手くなりたいのであれば、必ず習得しなければいけないものといえます。
リズムによっての使い分けの詳しい話は別のところで記します。
1つのテンポの中でも
「四分音符ならこの叩き方」
「八分音符ならこの高さ」
「十六分音符なら肘を動かす範囲はここまで」
といったように、その音符の長さによって叩き方を変化させます。
これが打楽器奏者特有のリズムの取り方のコツです。
音符ごとに音量がデコボコしないように厳密に調整しながら、
音符と音符の間に生じるタイミングを、腕の動かし方の変化で取る。
この技術を会得するためにとんでもない時間を掛けてゆくこととなります。
もしあなたが打楽器を演奏する技術を磨こうとしているのならば、あなたもその一人です。
それが出来るようになるために必要なテクニックを、ひとつひとつこれから紐解いていきましょう。
まとめ
スティックはてこの原理のように『力点』『支点』『作用点』がある。
その中でも『支点』となる軸が決してブレてはいけない。
テンポやリズムの変化に応じて、腕の使い方が変化する。
『肩』『肘』『指』の動かす割合を使い分ける。
音符ごとに音量がデコボコしないように厳密に調整しながら、
音符と音符の間に生じるタイミングを、腕の動かし方の変化で取る。
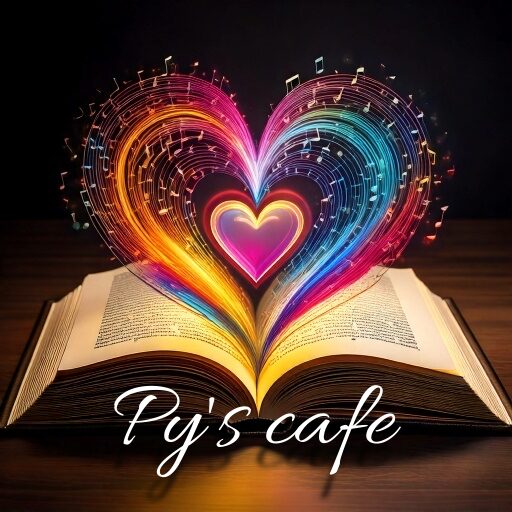 Py’s cafe
Py’s cafe 


