五線と加線
音を視覚で認識できる形に具現化する手法は、さまざまなやり方によって確立されてきました。その歴史は10世紀頃まで遡り、物によれば18線のものまでありました。
現在使われている五線譜は15世紀頃から使われ始めているものです。
楽譜を読みなれない人からすれば「なんでこんな読みにくい方法で!」と思うこともあるかもしれませんが、長い歴史を経て現在に残された記譜法としてこの形式だけが一般的に用いられているということは、結局この五線譜が最も合理的で最も分かりやすいものであると言えます。

西洋音楽史の勉強をすれば必ず『ネウマ譜』や『定量記譜法』といった昔の記譜法を知ることとなりますが、それらと比較すれば、現行の五線譜が一番情報を詰め込みやすく、かつ素早く多くの情報を読み取れる方法だというのが分かります。
otttava(オッターヴァ)記号
あまり五線から上下へ出てしまうと加線が多くなり読みにくくなってしまいます。
そのため、1オクターブ上下を簡易的に示し読みやすくするottava記号が用いられます。
all’a ottava(アロッターヴァ)
all’a ottava alta(アルタ)
書かれた音より1オクターブ高い音を演奏することを『all’a ottava alta』と呼びます。

all’a ottava bassa(バッサ)
書かれた音より1オクターブ低い音を演奏することを『all’a ottava bassa』と呼びます。

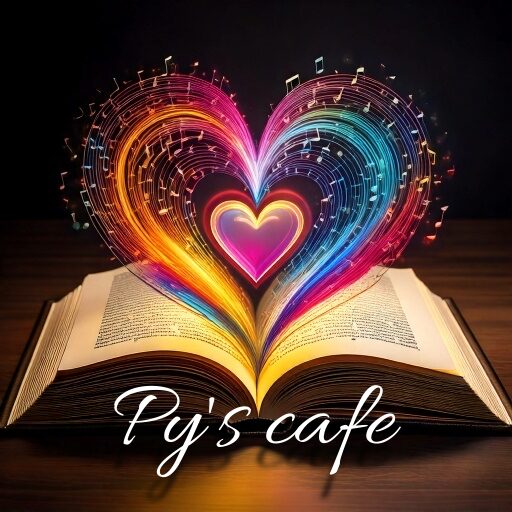 Py’s cafe
Py’s cafe 

