コントラバスやチューバのような低音があれば、バイオリンやフルートのような高音も存在します。それぞれの楽器の音を五線で表記するには、それぞれの楽器の音域に合った音の高さを指定する必要があります。
『音部記号』とは、五線上の音の高さを定めるために用いられる記号であり、音部記号が五線に記載されたものを『譜表』と呼びます。
ト音記号

高音の楽器を演奏するときに用いられます。別名『高音部譜表』とも呼ばれます。
主に、女声(ソプラノ・アルト)・バイオリン・フルート・クラリネット・オーボエ・サックス・トランペット・ホルンは、このト音記号で示されます。
この記号の渦巻の中心にある音が「ト音(ソ・G)」であることから『ト音記号』といわれています。
ちなみにこの記号を書くときは、中央の渦巻きから書き始めて上部で折り返し、下部で終わります。

ヘ音記号

低音の楽器を演奏するときに用いられます。別名『低音部譜表』とも呼ばれます。
主に、男声(テノール・バス)・チェロ・コントラバス・ファゴット・バストロンボーン・チューバ・ティンパニは、このヘ音記号で示されます。
この記号の玉の部分(2つの点の間)の音が「へ音(ファ・F)」であることから『ヘ音記号』といわれています。

この2つの音部記号で、ほとんどの楽器は充分に音を示すことが可能となります。
しかしながら、この2つのどちらであっても読むのが困難となってしまう音域をもつ楽器が、主に2つあります。
それが、中低音の音域を専門とする『ヴィオラ』と『トロンボーン』です。


この2つの楽器は、ちょうどト音記号とヘ音記号の間辺り、すなわちハ音(ド・C)の周辺の音域を専門としています。
それゆえ、ト音記号で示すと下線が頻繁に登場する楽譜となってしまいます。
反対に、ヘ音記号で示せば上線が頻繁に登場する楽譜となってしまいます。
そのため、ト音記号とヘ音記号の間の音域を表示するための『ハ音記号』と呼ばれる音部記号が存在します。
ハ音記号

この記号の中央が「ハ音(ド・C)」であることから『ハ音記号』といわれています。
別名『中音部譜表』とも呼ばれます。
五線の第三線がハ音となるこの音部記号は『アルト記号』といわれています。
ヴィオラはこのアルト記号が用いられます。
ハ音記号には、音の高さをここから上下にズラした5つの種類があります。
1)ソプラノ記号

ト音記号の範囲よりちょっとだけ低い音域の際に用いられます。
あまり使われません。

2)メゾソプラノ記号

ソプラノ記号よりちょっと低い音域の際に用いられます。
こちらもあまりお見かけしません。

3)アルト記号

先ほど記載したもので、ヴィオラに用いられます。
ヴィオラに用いられるということは、オーケストラのスコアには必ずといって良いほどこのアルト記号が書かれています。
音楽理論・移調・スコアリーディング等の際には是非とも読めるようになっていた方が良い音部記号ですので、勉強しておくことをおすすめします。

4)テノール記号

アルト記号よりちょっと音域が低い音部記号で、テナートロンボーンは主にこの音部記号が用いられます。(但し、吹奏楽ではほとんどヘ音記号で記される)
また、チェロやファゴットの記譜に用いられることもあります。
ハ音記号の中では、アルト記号とテノール記号に馴染んでおくことを推奨します。

5)バリトン記号

ヘ音記号よりちょっと音域が高い音部記号です。
しかし、現在はほとんど使用されていません。

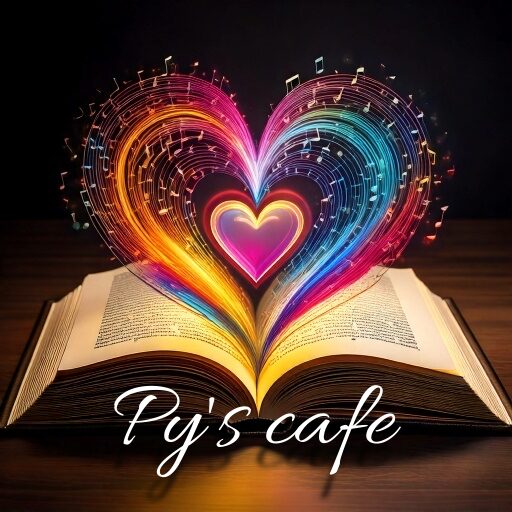 Py’s cafe
Py’s cafe 
