人によって手の大きさや指の長さが異なるため、厳密な定義はありません。
しかし、楽器を鳴らすための理に適ったやり方はあります。
無秩序な奏法でいると、身体が余計なエネルギーを浪費したり、楽器にダメージを蓄積させてしまうことにも繋がります。
初心者の方はひとつひとつをじっくりと確かめながら、経験者の方は自分のやり方ひとつひとつが本当に合っているのかしっかり確かめながらチェックしてください。
原則は、スティックが振り子のような一定運動をストレスなく行える持ち方になります。
この動きを妨げない持ち方が基本です。
スティックの軸

この軸の位置は『スティックの下から1/3地点』が基本となります。
スティックの形状などによってはこの位置が変動しますが、ほとんどのスティックの形状はほぼ同じなので、よほど変わったものを使わない限りは1/3と覚えておいて良いでしょう。
スティックの中心部に近い位置を軸にしてしまうと、スティックの『振り子のような動作』にかなり制限をかけてしまうため、楽器を十分に鳴らすことができなくなってしまいます。
逆にスティックの根本寄りを軸にしてしまうと、スティックを振るための力が本来のエネルギー以上に必要となってしまうため、腕や手首に余分な負担を掛けさせてしまいます。
ティンパニやバスドラム、マリンバなどの鍵盤楽器のマレットの持つ地点はそれぞれ異なる理由がありまた違います。
「この形状のスティックは下から1/3地点を軸にした持ち方」と覚えましょう。
スティックの持ち方
手でスティックを持つ時の説明です。
上記の『スティックが振り子のような一定運動をストレスなく行える持ち方』をするための方法なので、とても重要なポイントとなります。
親指と人差し指
指先はやがて細やかな操作をするために取っておくので、スティックを持つためには指先を使いません。
指先でスティックを持たないようにしましょう。
親指の爪の根本付近と人差し指の第二関節のおよそ『側面』同士でスティックを軽く挟む形が望ましいです。

指の側面ではなく指の腹側で挟む形になってしまうと、親指と人差し指が『挟む』動作以外を全く行えなくなってしまいます。
人差し指の指先は速いリズムを刻むために使うので、軸より根元側でスティックを触れるようにする必要もあります。
これらを理由に、指の側面で持つ感覚を養いましょう。
持つ(挟む)チカラは最小限
挟む力はほとんど要りません。
「皮膚がスティックに引っ掛かって滑らない」程度の感覚で充分です。
スティックを持った後、誰かにこのスティックをそっと引っ張ってもらったら、「腕が吸い寄せられるようにスティックについてくぐらいには脱力」していて、でも「手からはスティックが離れない。」そんなレベルの力加減です。
言葉で説明するとどうしても難解になってしまうので申し訳ありません・・・。
とにかく、「スティックを持つのにできる限りチカラを使わない」と「どれだけ速く激しく叩いてもスティックが手から離れない」を共存させなければいけないのです。
その為の技術がここに集約されています。
ちょくちょくスティックが手からすっぽ抜けてしまう打楽器奏者を見かけますが、その原因はこの一点にあります。
親指と人差し指の間
スティックと非常に接しやすい『親指と人差し指の間』ですが、ここは基本的にはスティックと接しません。
無理に意識して触れないようにするのは、逆に不自然な持ち方になってしまう可能性があるため良くないです。自然にスティックが母指球や手首側の生命線に触れる位置にくれば、『親指と人差し指の間』と『スティック』の間に隙間が空く状態にならないでしょうか。

中指・薬指・小指
この3つの指は打楽器を叩く寸前に使う時があるだけのものであり、基本位置はスティックに触れません。
そして非常に重要なのが、「指が伸びないこと」です。
これは親指と人差し指を含む全ての指に該当します。
身体のどの部位でも言えることですが、関節が伸びている状態は筋肉が緊張している状態です。
打楽器の演奏において筋肉を緊張させる必要はほとんどありません。
基本的にスティックやマレットの遠心力や重力を利用して打楽器を叩くのが基本ですので、筋肉は腕を動かしたりする程度にしか活用する必要がないのです。
指が伸びている状態ということは、指が緊張し、演奏に必要のないエネルギーを浪費してしまっている状態といえます。関係のないところで疲労してしまう原因となるので、関節は伸ばさないように注意しましょう。
特に、小指がピンと伸びてしまう人が非常に多いです。
中指・薬指・小指の3つの指は『卵を優しく包み込むような形』を常に意識しましょう。
『指の関節全て緩く曲げておく』くらいの感覚と覚えておいても大丈夫です。
スティックの根本
親指と人差し指の側面で挟む。それだけではまだ十分な形にはなれません。

こちらの2つの持ち方はどちらも正しくありません。
どちらもスティックの軸が一点に定まらず、動作が不安定である上、スティックに遠心力や重力が掛かり辛く、しかも指で必要以上にスティックの動きを制御してしまうため、結果として良い音がかなり鳴りにくくなってしまいます。

こちらが理想的な形です。
生命線に沿うようにスティックの根元側が通るのが正しく、この形であればスティックの『振り子のような一定運動』を指や手が阻害しにくくなる自然な形になります。
この形のまま手の甲を上に向けると、スティックの根本側はほとんど腕に隠れるような状態になるのではないでしょうか。
『肘からスティックの先端までが一本の直線を結ぶように真っ直ぐ出来ている状態』を覚えておきましょう。

図のように、上から見るとだいたい三角形に近い形を作ることができます。
この形をイメージしてスティックを持つと、良い状態が生まれやすいかと思います。
また、上図のように構えた時、左右の手首から身体から同じ距離になっているにも関わらず、2本のスティックの先端がおへその真正面に位置しなければ、スティックを持つ位置がどちらかズレていることになります。
スティックを持つ時、必ず左右とも全く同じ位置を軸にできるように、2本とも持つ位置をきっちり揃えるクセを身につけましょう。
まとめ
スティックの軸は下から1/3。
持つ位置を左右ともきちんと揃える。
親指の爪の根本辺りの側面と、人差し指第2関節の側面で、最小限のチカラで挟む。
全ての指の関節を軽く折り曲げる。特に中指・薬指・小指は、卵を包み込むような形で。
スティックの根本は生命線を沿うように。腕とスティックは一直線を描くように。
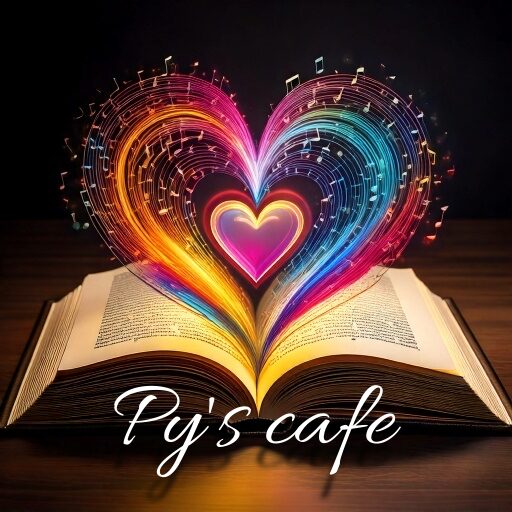 Py’s cafe
Py’s cafe 

