『持ち方』の次は『立ち方』です。
「細かいな〜!!」と思うかもしれませんが、この初歩の段階を『なんとなく』でよく考えずやってしまっては、後ほどとんでもない目に遭ってしまう上にそのクセを修正するのがとてつもなく大変になるのです。
今まで右利きで文字を書いていたのが、ある日急に左利きに直そうとしたってムチャな話です。書けるようになるには相当な時間と苦労が必要です。
その相当な時間と苦労が、この初歩の段階で悪いクセをつけてしまった時に修正する時にも発生してしまうのです。
頭のてっぺんから足の先っちょまで、全ての所作の理由を説明できるくらい、徹底的に演奏のための動作について理解するつもりで勉強しましょう。
足の重心位置

何も考えず自然に立っている時は、一般的に、両足のかかとにだけ体重がかかっており、ちょうど両方のかかとの間の位置に身体や頭部が来ていることが多いのではないでしょうか。
学校や会社などで「気をつけ」の姿勢を教わりますよね。背筋をピンと伸ばし、頭からかかとまで縦一直線になるような姿勢をするように習ったかと思います。
・・・その姿勢って、実は身体に良くない『悪い立ち方』なのです。
足の構造上バランス良くどっしりと構える為には、足全体を使って体重を支えた方が本当は良いです。
膝や腰に対してもこの方が負担が軽くなるので、演奏の為どころか、この際健康のために是が非でも覚えておきましょう。

まず、足に体重を乗せる場所は片足につき3カ所あります。
『親指の付け根』
『小指の付け根』
『かかと』
この3か所に対して均等に体重を乗せる立ち方が、正しい形となります。
そして、各足の体重を乗せる場所から結んだ中心点となる位置が『重心位置』となります。胴体や頭部がこの位置にくるわけです。
『気をつけの姿勢』よりちょっと前傾姿勢になれたら、正解です。
緩く立つ
先ほどの『気をつけの姿勢は身体に良くない立ち方』から続く話なのですが、肩・背中・腰・膝をピンと真っ直ぐ張って立つやり方は理にかなっていません。
何より、最終的に打楽器の演奏で最も集中したい場所は、身体のどこでもなく『スティックの先端』です。
基礎技術の最終的に行き着く先は、「身体の状態なんて一切気にせず、スティックの先端にだけひたすら意識を向け続け、どんな繊細かつ難解な技巧でも思い通りに奏する技術を習得する」です。
そこへ向かうためにも、身体の状態は何にも気にする必要がない形に予め完成させておきたいのです。
そのために望ましい身体の状態とは、演奏するために必要な腕やスティックの動作を行うのに対し、必要となるどんな動作にも柔軟に対応できるしなやかな基盤です。
そこで、しなやかな基盤づくりとして『猫背』の姿勢をおすすめします。
理由は、これが『脱力』しやすい状態のためです。

『猫背』といっても、健康上の問題となるほど背中を曲げるわけではありません。「背筋をピンと伸ばすのではなく、チカラを抜いて背中をゆる〜くしておく」という意味での『猫背』です。
たっぷり深呼吸ができるくらいには胸側を開いておくようにしないと、かえって身体に緊張状態を生み出しかねません。
深呼吸もでき、背中も脱力できる上半身の状態を意識しましょう。
そして、『スティックの持ち方』での話で「関節は筋肉を緊張させない為にも全て軽く曲げておく」と説明していましたが、それは全身にも言える話です。
肩・肘・膝も同様に、筋肉を緊張させないよう、軽く曲げて脱力をさせておきましょう。
余談ですが、電車の中で『両足6か所で取る重心の取り方と全身を脱力させるための緩い立ち方』を実践すると、『気をつけの姿勢』の時よりも断然ふらつきにくくなります。ブレーキなどによって変化させられる体重移動に、身体が柔軟に対応しやすくなるからです。
重心バランスを6カ所に分散していると体重移動が前後左右どこにでも変化しやすいですし、膝や腰を柔らかくしていると、下半身と上半身がバネで接合されているかのようにしなやかになります。
普段の日常生活から意識してこの姿勢でいると、練習の時にわざわざ意識する必要がなくなって美味しいので、他人に迷惑かけない範囲で実践してみてください。
まとめ
両足の『親指の付け根』・『小指の付け根』・『かかと』の3点を使って立つ。
重心位置は両足の土踏まずの間。つまり前傾姿勢。
肩・背中・腰・膝を脱力。ピシッと立たない。
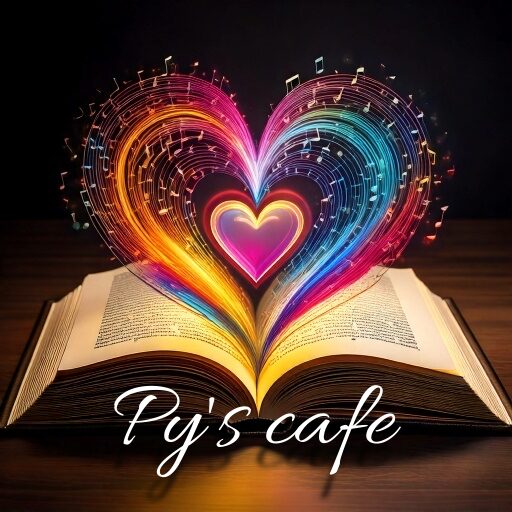 Py’s cafe
Py’s cafe 


