『持ち方』『立ち方』の次は『構え方』です。基本姿勢3つのうちの最後となります。
これら基本姿勢を覚えたら次はやっと打楽器奏者らしくなれる『叩き方』編ですので、正しい姿勢で『叩き方』を覚えられるように、『構え方』をきちんと覚えていきましょう。
ハの字を作り、スティックは下向きに

打楽器を叩く位置が左手と右手で異なってしまうと、『音色』が左手と右手で異なり、そのせいで不揃いな聴こえ方になってしまいます。

ほとんどの打楽器の打面は円形であり、叩いた地点から打面全体へ広がるように、細かく激しく振動します。
池に石を投げ込んだら、ポチャンと石が沈んだ場所から何重にも連なった波紋が広がってゆくのは分かりますか?それと全く同じ原理が打面にも起きているのです。

その仕組みのせいで、物理的な論理([波]の性質)に基づくと、叩く位置は『左手と右手がどちらも打面の同じ円周上』でないと「左手で叩いた時の音色」と「右手で叩いた時の音色」がズレてしまいます。
『左手と右手がどちらも打面の同じ円周上』であれば、「左手で叩いた時の音色」と「右手で叩いた時の音色」は同じものとなります。
叩くことによって打面上に発生する波形が同じであればあるほど、同じ音色が鳴ることになります。同一円周上であれば波形の広がり方・反射の仕方・波同士のぶつかり方が同じとなります。極端に言えば、右手は右奥、左手は左手前であっても、同一円周上なら同じ音色となるのです。
(しかしながら、同一円周上であることを見極めるためには、結局叩く場所ごとの音色の違いが分かる必要があるので、一通りの基礎を習得するまでは『右手でも左手でも同じ場所を叩く』を徹底するに越したことはありません。なので、『ハの字』を作ってスティックの先を揃えます。)
叩いてる本人にはこの違いがとても聞き分け辛いのですが、コンサート会場のような大きい空間での客席で聞くと分かりやすくなります。
特にコンクールやコンテストともなると審査員は間違いなくプロです。そのくらいの音色の違いはわかって当然なので、右手と左手の音色が揃っていないだけで技術が未熟だと判断されます。
どれだけたくさん練習を重ねたところで、こんな初歩である構えの段階が不安定なせいで評価は得られない、ということです。
とても重要なので必ず覚えておきましょう。
叩いている最中でも、ハの字と下向きを維持

この『ハの字』と『スティック先は下向き』の意識が最も薄れやすいのは、叩いている最中です。
叩く時は両手を交互に振り上げと振り下ろしを行います。
つまり、片方の手が振り上げているときは、もう片方の手は動作する必要がありません。
動作しない手は常に『基本の構え』の位置、すなわち『ハの字』と『スティック先は下向き』の形に必ず戻します。
実際に指導している中で、これが守れない生徒が非常に多かったです。
どうしても叩くことに意識が向いてしまうので、叩いていない手まで注意がいかず、おろそかな状態となりやすいです。
いつでも、叩いていない時と叩いた直後は原則として『基本の構え』の位置にリセットする。これを徹底的に身につけましょう。
左右対称

構えた時の体勢は、右半身と左半身で異なる要素があってはいけません。
これを確認する方法は、誰かにチェックしてもらうか、鏡など自分の姿が映るものを使うか、自分の姿を録画するかの3つが基本的な選択肢かと思います。
これらの方法を取らずに、自分が構えてる時の体勢をその場で目視だけで確認するのみ、というのが一般的にやりがちとなります。
実際問題、部活で姿見のような鏡がある環境は中々ないでしょうし、部活中にスマホが使えない(持ち込めない)ため録画出来ないなんてこともあるでしょう。
他の人は自分の練習しているから、いちいちチェックしてもらう為の時間を取ってもらうなんて選択も難しいでしょう。
打楽器パートに同期が居ればまだ可能かもしれませんが、少人数のチームも多くなっている昨今、それもあまり現実的ではないでしょう。
けれど、悪いクセは気が抜けた時に必ず出ていて、それが気付かないまま定着していきます。
ぶっちゃけ、楽器やスティックがなくとも構えは作れます。なので部活中に限らなくとも、家でも確認することは出来ます。
楽器なんて無くとも、一瞬で一定の構えが作れるぐらいまでは、徹底して構えが左右非対称になってないかチェックするクセが必要です。
脇は拳一つ分だけ空ける
脇は閉じていても、また開き過ぎていてもいけません。
もちろん打面の高さや距離が調整出来ない場合があるので、その時は脇の開き加減(肘の高さ)を調整することがあります。ただ、それは例外として扱うものであり、まず原則とする姿勢を定着させましょう。
その定義が『脇は拳一つ分』です。
これはどんな身長でも関係なく統一します。
脇にぴったりくっ付けるように握り拳を入れ、脇をそっと挟むように軽く閉じましょう。
その時に出来る胴体と肘の間の距離を、よーく覚えておきましょう。
これが基本の構えの最も重要なポイントです。
手首は曲げず伸ばさず
これは腱鞘炎予防の為の対策です。
基本の構えにおいて手首は、「伸ばす」でも「曲げる」でもなく、「自然体のまま」が望ましいです。
手首は思っているよりも脆い部位です。不自然な状態を継続してしまったり、負荷を掛け続け手首の筋が耐え切れなくなってしまったら、腱鞘炎となり故障します。そのなると以降は故障癖がついてしまい日常生活にすら悪影響を及ぼしてしまう重大な問題となります。
せっかく全身を脱力させるのです。手首だって例外でなく、脱力出来る自然体をキープした状態を基本の構えとして定着させましょう。
肘は身体より後ろへは引かない

指導者でこれを気にする人は多くないと思いますが、腕を自由に動かすために重要なポイントです。
肘が胴体より後ろ側へ引いていると、腕を振り上げたり振り下ろしたりするのに充分な可動域を確保できません。
やってみると分かると思いますが、肘の位置が前後で変わるだけで、腕を振り上げた時の脇の開き具合が大きく異なります。
肘が胴体と同じくらいか、わずかに前の位置にしていれば、肩周りの動きが制限されず自由に腕を動かせます。
まとめ
ハの字を作って、スティックの先端は下向き
左右対称の姿勢であること
脇の開き具合は拳一つ分
手首は自然な状態を常に保つ
肘の位置は胴体の真横か少し前へ
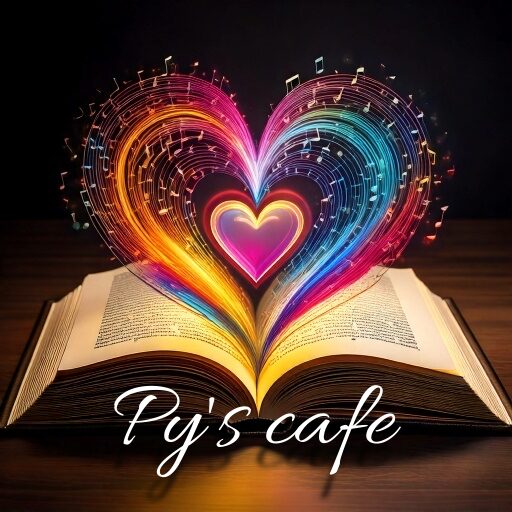 Py’s cafe
Py’s cafe 



