ここからはいよいよ、叩くための動作についての話をなります。
叩くための動作は『振り上げ』『振り下ろし』の2つに分けます。
『打楽器を鳴らすための動作』でまとめた内容とはまた別で、「振り上げること」自体に焦点を置いた内容をまとめます。
タイミングの取り方

演奏者であるためには、リズムとタイミングを正確に取れるようになる必要があります。
打楽器においてのタイミングの取り方のポイントは『叩く時』ではなく、『叩くために振り上げるタイミング』でコントロールします。
例えば、合わせシンバルをffで叩く時は、両腕を大きく広げてから素早くシンバル同士をぶつけます。
これにおいて、「両腕を大きく広げる」という動作を行ったら、タイミング調整をするために停止したり閉じる速度を途中で変えたりしてはいけません。
あくまで、「両腕を広げる→両腕を閉じる→シンバル同士がぶつかり、音が鳴る」までが一連の動作としてセットになるものです。
極端に言ってしまえば、間違ったタイミングで腕を広げてしまったなら、間違ったタイミングそのままでシンバルを鳴らしてしまえ。という話です。
これが、スティックを使って太鼓を叩く時にも同様のことが言えるのです。
よく打楽器の基礎練習を指導する時に見られるのですが、『振り上げ』をした後、『振り下ろし』をする前に片腕でスティックを掲げたまま停止している生徒を頻繁に見かけます。これはNG行為です。
基本的に『振り上げ』の動作と『振り下ろし』の動作は、それぞれ一定のスピードで行うものです。そして、『振り上げ』と『振り下ろし』の間に停止する時間は一切つくらず、必ず連続して動作します。
肩甲骨から

「腕」と呼ばれる部位は、「肩」から始まります。
腕が自由に動くために、鎖骨や肩甲骨といった首周りや背中の骨まで連動するのはご存知でしょうか。実際に鎖骨や肩甲骨を触りながら腕を上げたり下ろしたりしてみると、一緒になって動いているのが分かるかと思います。
この鎖骨や肩甲骨が一緒になって動いていることを意識できているかどうかが重要で、これだけで肘の可動域が大きく変わります。
スネアドラムを叩くときには、実際は肩甲骨まで使って腕を動かすことはあまりありません。けれど、バスドラムやティンパニ、マリンバなどでは肩甲骨まで使うほどに腕を動かすことが基本形となるほど、動きが大きくなります。
基礎の打楽器演奏の動きとして定着しておきたいので、肘が動く限りは肩甲骨まで連動している感覚を忘れないようにしましょう。
「腕」も「スティック」も同時に始動

これも吹奏楽部の練習現場でよく見る光景なのですが、振り上げる時、腕を上げてから手やスティックがついてくるように上がるパターンと、逆にスティックが先に上がってから腕がついていくように上がるパターンが見られます。
これは両方ともNGです。
打楽器指導者の中にはこのムチのような動き方を教える人もいますが、これでは必要充分なエネルギーを楽器に適切に伝えることができません。
振り上げるときは、腕も手もスティックもピッタリ同時に上げます。
『振り上げ』と『振り下ろし』において、スティックに伝えたいエネルギーは『重力』と『遠心力』だけです。
前述した通り、『振り上げ』と『振り下ろし』は一連の動作です。『振り上げ』で余計な動作を起こせば、必ず『振り下ろし』の動作にもその影響を及ぼします。
『振り上げ』の時に腕が先行して振り上げてしまうと、必然とスティックはムチがしなるような動作となってしまいます。
こうなってしまうと『振り下ろし』の時にスティックへ必要以上の遠心力がかかってしまい、打楽器へ強い衝撃を与え「痛い音」が鳴ってしまいます。
『振り上げ』の時にスティックが先行して振り上げてしまうと、『振り下ろし』を始めた時に腕はやっと振り上げ終わるという遅れた動作となってしまいます。
腕の動きとして不自然となってしまうために肘周りに負荷を掛けますし、スティック先にも振り上げた分の重力と遠心力が充分に伝えられず、エネルギーとしては不足します。こうなると楽器はまともに響きません。
一番のミソは、腕を上げた時に手首がダランとしないようにすることです。
最高到達地点が頭より後ろへ行かないように

振り上げ切った時についてです。
振り上げの最高到達地点ですが、基礎練習でテンポ60の四分音符くらいの速さならば、腕(肩から肘まで)は地面と水平になるくらい動かしましょう。
指導する生徒たちの基礎練習を見ると、全くと言って良いほど肘が動かない人が非常に多いです。
しかし、楽器の大きさやリズムの速さによって腕の動きは変化させるのが打楽器奏者の基本です。
いつでもどんな楽器やどんなリズムにも対応できるようになるためにも、しっかり腕を使い肘を動かすことを、基礎練習の段階で意識しましょう。
では、高く上げれば良いというものでしょうか。
振り上げる目的は、主に「腕や肩甲骨を充分に使うこと(やがてウォーミングアップ目的)」と「スティック先に必要十分な『重力』と『遠心力』を伝え楽器を綺麗に響かせること」の2つです。
この2つさえ達成できれば、不要な要素はなるべく削ぎ落としておきたいところです。
無駄に動きが大きくなってしまっても、非常に大きな宮太鼓を叩く以外に使い所がありません。なので、ティンパニなどで使い得る範囲に収めます。
そのポイントが、『テンポ60の四分音符くらいの速さまでならば、腕(肩から肘まで)は地面と水平』を最高位置とし、『手首の位置は頭部よりも前側』であることを意識しましょう。
この時『スティックの持ち方』で説明した、「中指・薬指・小指は伸ばさず卵を包むような形であること」と「スティックの根本は生命線に沿うこと」の2点をきちんと維持できていることが大切です。
振り上げ切った時に、スティックの根本は薬指や小指の指先辺りに当たっており、スティックは後ろに30°程度の傾きで止まっているはずです。
これがどちらかでも満たしていない場合、指が構えの時より開いてしまっている状態になっています。手や指の形は、振り上げても変わらないようにしましょう。
振り上げの軌道は最短距離を

かなり細かい話ですが、振り上げの軌道が寄り道気味な人がほとんどです。
タイプとしては2通りあって、振り上げをする時に一度肘を前へ突き出すように腕を伸ばす人と、スティック先が構えの位置より左右にブレながら振り上げる人がいます。
どちらにしても叩くための動作として不要ですし、余計なエネルギーや負荷がかからないようにするためにも、肘・手首・スティック先の軌道は一定の最短距離を常に描けるように意識しましょう。
まとめ
『振り上げ』を始める瞬間で、叩くタイミングが決まる
腕は肩甲骨から動かす
腕とスティックがバラバラに動かない
テンポ60の四分音符程度までのリズムの速さなら、腕(肩から肘)はおよそ水平にまで上げる
手の形は振り上げても構えの時から変わらない
振り上げの軌道は最短距離を常に描く
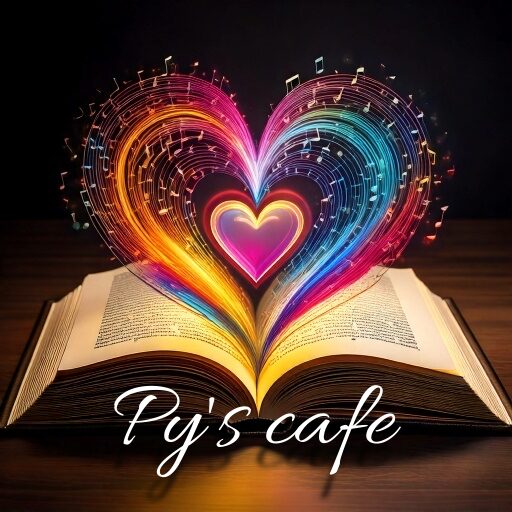 Py’s cafe
Py’s cafe 


