『振り上げ』・『振り下ろし』の一連の動作を基本の動作としてまとめました。
ですが、それだけではアクセントや急激な強弱変化などに対応できません。
『振り上げ・振り下ろしの一連の動作』によって制御できるのは、一律な振り上げの高さです。
「フォルテはこの振り上げの高さ、メゾフォルテはこの振り上げの高さ」というように、曲毎にそれぞれの強弱記号に対する振り上げの高さを設定しておくと、クレッシェンドやデクレッシェンドの変化に安定性・再現性を与えることができます。
演奏する度に変化の度合が意図せず変わるのは演奏者として欠陥となるので、これはこれとして非常に大切なことです。
今回の『ストローク4種』は、アクセントやフォルテピアノなどの唐突な音量変化に対して有効な技術です。
連続した音符の様々なヴァリエーションに合わせて、次のストローク4種類を、『振り上げ・振り下ろし』の動作と複合させて行います。
ストローク4種類

音符によって叩き分ける種類は4種類あります。
これは、『鳴らす音符にアクセントがあるか』・『直後の音符にアクセントがあるか』という2つの分類で振り分けます。
ダウンストローク

『鳴らす音符にアクセントがある』ことと、『直後の音符にアクセントがない』ことが条件に適合するときに使用する叩き方です。

アクセントの定義としては「大きく鳴らす」ではなく「強調する・ハッキリさせる」です。特別音量を大きくする必要はないのですが、周りの他の音符よりも際立って聞こえるように叩かなければいけません。
そこで、アクセントの付いた音符は通常の振り上げよりも高く振り上げて、通常の音符よりエネルギーを増加させます。
『ダウンストローク』は、あらかじめ通常より大きめに振り上げ、叩いたら通常の振り上げの高さへ戻す叩き方です。
直後が休符の場合は、そのまま構えの位置で停止します。
フルストローク

『鳴らす音符にアクセントがある』ことと、『直後の音符にアクセントがある』ことが条件に適合するときに使用する叩き方です。

『フルストローク』は、あらかじめ通常より大きめに振り上げ、続いて次のアクセントのついた音符を叩く為に同じだけ振り上げます。
「わざわざ再び振り上げる」のではなく、「スティックが跳ね上がるエネルギーを利用して振り上げの高さまで戻す」イメージが重要です。
ずっと『フルストローク』を繰り返す練習を、『リバウンド練習』の課題で行います。
バスケットボールのドリブルのように、『スティックが重力で落ちてゆく』動きと『スティックがリバウンドで跳ね上がる』動きの2パターンを淀みなくずっと繰り返します。
ダウンストロークとの違いは、次に叩く音符が「アクセントがある」か「アクセントじゃない」か、という点です。叩く音符自体ではなく、次の音符で判断するので、譜読みの時にきちんとチェックし区別しておきましょう。
アップストローク

『鳴らす音符にアクセントがない』ことと、『直後の音符にアクセントがある』ことが条件に適合するときに使用する叩き方です。

ダウンストロークやフルストロークとの違いは、「叩く音符にはアクセントがないこと」です。
なので、この『アップストローク』によって叩く音符自体は、通常の音符となんら差がないようにしなければいけません。
「アクセントのついた音符は強調する」を成立する為には、アクセントのついていない通常の音符は全て同じ音量で統一する必要があります。
アップストロークもこれに該当します。
タップストローク

『鳴らす音符にアクセントがない』ことと、『直後の音符にアクセントがない』ことが条件に適合するときに使用する叩き方です。

この叩き方は、すなわち「アクセントの音符とは関係ない、ただの通常音符」です。
基本的に音符にアクセントがつく場面は偏りがあり、八分音符や十六分音符など細かいリズムが連続する時が頻用されます。
この場合は振り上げをしている時間がほとんどなく、もはや「振り上げ」と呼べる動作を行わなくなります。
振り上げず、構えの位置からスティック先を落とすだけの動作。『タップストローク』は基本的にそんな動作を指します。
『振り上げ・振り下ろし』と『ストローク4種』の区別
『振り上げ・振り下ろし』の叩き方と、『ストローク4種』の叩き方はどう違うのか?
どう使い分けるのか?
そもそも『振り上げ・振り下ろし』は、叩き方そのもの自体の内容であり、
『ストローク4種』は音符によって異なる叩き方を使い分けるための内容です。
つまり、『振り上げ・振り下ろし』と『ストローク4種』は常に両方行うこととなります。
『ストローク4種』は、アクセントがある音とアクセントがない音、すなわち2段階の音量差異を生み出す技術です。
「pp・p・mp・mf・f・ff」の音量記号6つにそれぞれ『ストローク4種』の2段階で叩き分けをするということは、
6×2=12段階の音量・振り上げの高さを設定するということです。
ゆえに、12段階の『振り上げ・振り下ろし』をするということです。
もっと言えば、リズムの細かさやテンポの速さによって『振り上げ・振り下ろし』は変化しますから、そうなると12段階どころではありません。
フレーズを付けるために、同じ音量・同じリズムでも微弱な強弱変化をつけたりも、やがてする必要があります。

なので、打楽器奏者として上達するためには100段階以上の音量変化(振り上げ・振り下ろし)ができるようにならなければいけません。
それだけ、この『振り上げ・振り下ろし』と『ストローク4種』については思っている以上に奥深い内容なのです。
打楽器奏者であるなら、今後ずっと研究し続ける要素であることを心に留めておきましょう。
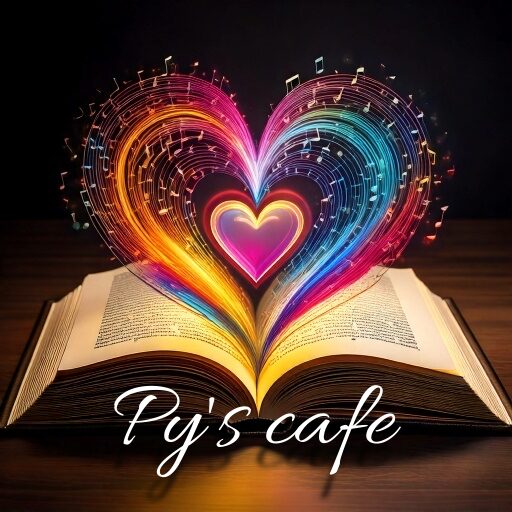 Py’s cafe
Py’s cafe 


