
度数について詳しく説明していきます。
度数の数値は、常に変化記号(♯や♭などの調号や臨時記号)の影響を受けません。
「C♯」も「C」も「C♭」も、ここでは同じ音として扱います。
単音程
1度から8度までの範囲での音程を『単音程』といいます。
1度(ユニゾン)

同じ音の高さを「1度」もしくは「同度」といいます。
例のように、「A」と「A」、「D」と「D♭」、「G♭」と「G♯」のどれも『1度』として扱います。
このようにどんな変化記号がついても、音名が同じならば全て『1度』となります。
2度

音の高さが隣り合う音程を「2度」といいます。
「A」と「B」、「E」と「D♭」、「D♭」と「C♯」などが例に挙げられます。
隣の音名であれば、上下問わず度数は『2度』です。
3度

音名を1つ飛ばした音程を「3度」といいます。
「2度」より音名1つ分離れている為、音程幅が増加し「3度」となっています。
「B」を挟んだ「A」と「C」、「E」を挟んだ「F♯」と「D」、「A」を挟んだ「B♭」と「G♯」などが例に挙げられます。
4度

音名を2つ飛ばした、「3度」より音程が1度分増加した音程を「4度」といいます。
以降も同様に音程幅が音名1つ分離れるごとに度数が増加していきます。
5度

6度

7度

8度(1オクターブ)

複音程
1オクターブより広い範囲の音程のことを『複音程』といいます。
基本的に「○オクターブ + ○度」と表せるものは全て該当します。
9度(1オクターブ + 2度)

『“1オクターブの音程幅” + “2度の音程幅”』=『9度』となります。
音程の扱いとしては、2度と同等と考えて良いです。
『音程の種類』において、音程について更に複雑な内容が登場しますが、このとき「2度=9度」「3度=10度」「4度=11度」「5度=12度」「6度=13度」「7度=14度」「8度=15度」と思って良いです。
10度(1オクターブ + 3度)

『“1オクターブの音程幅” + “3度の音程幅”』=『10度』となります。
以降、
『1オクターブ + 4度』=『11度』
『1オクターブ + 5度』=『12度』
『1オクターブ + 6度』=『13度』
『1オクターブ + 7度』=『14度』となり、
『1オクターブ + 8度』=『15度』=『2オクターブ』となります。
ただ、実際に鳴らした時の響きは当然ながら異なります。
2度や7度など、場合によっては不快な響きをもたらす音程がいくつか存在します。
一般的に「不協和音」と呼ばれているものがその例となります。
そんな不快な響きでも、音程を1オクターブ増加して「2度→9度」とすると、不快な響きが減少します。
「理論」と「実際の感覚」で使い分けが異なりますので、知識と経験を増やし理解を深めていくことをお勧めします。
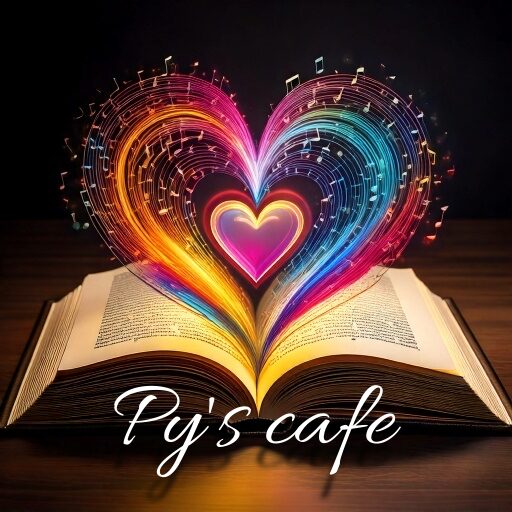 Py’s cafe
Py’s cafe 

